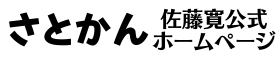脱学校化という考え方

いまさらですがイリッチさん
土曜日のゼミで、イヴァン・イリッチ『脱学校の社会(Deschooling Society)』(東京創元社 1977)を読みました。原書は1970年に最初の版が出ています。私が持っている本は1995年の第26版ですので、多分その頃に買ったのでしょう。それ以来四半世紀本棚に鎮座していたものの未読だったので、いまさら初めて読んだのでした。
有名な本なので、『脱学校』という概念はおおよそ知ってはいましたが、今回読んでみて改めて、イリッチさんの「お仕着せのカリキュラムによる人間の洗脳」に対する憎しみ、社会全体で「学校は善きモノ」と信じ込ませる呪縛への抵抗の激しさを感じました。
「学校」「工場」「病院」がいずれも、たかだか2-300年の歴史しかない「近代」の装置にすぎない、という主張はすんなりと理解できます。日本で言えば明治維新以来150年の歴史しかありません。しかし、今では近代化を始めたばかりの途上国を含めて世界中で「学校」は善きモノであり、学校にアクセスすることが人間性を開花させる唯一の方法であるかのように信じ込むまでになっていること、そのことの危険性をイリッチさんは50年前から主張していたわけです。そして、その頃からずっと熱烈なイリッチファンも絶えることなく存在するわけです。
布教・宣教・家父長主義
既に山ほどイリッチ研究者もいるので、いまさら私が付け加えるものなど何にもないのは承知の上で本書を読んだ感想です。イリッチさんの憎んでいるものの本質は「お仕着せ」「おためごかし」あるいは「パターナリズム(家父長主義)」であるように思います。あたかも、被教育者のためを思っているかのようなポーズを取りながら(あるいは心の底からそう思っていることも多いでしょう)、実際には学校という制度の中で人間を「近代人」として鋳型にはめるのが、学校という制度であり、そうしたことを当然視するのが「学校化された(schooled)」社会であるということ。
そして、こうした「学校化」は人間にとって決して良いことではなく、国家にとって、資本主義経済にとって好都合であるだけであることを指摘し、だからこれからは社会の『脱学校化』を目指すべきだ、と主張するわけです。
そして、「学校化」に対する嫌悪の背景には、イリッチさんのカトリックの聖職者としての経歴にたいする原罪意識があるようにも感じられます。本書を読みながらラス・カサス『インディアスの破壊についての簡潔な報告』(岩波文庫)を思い出しました。この本は1542年に新大陸を見聞したカトリックの司教が、キリスト教の布教と文明の名のもとにスペイン人が、現地人(インディアス)をいかに極悪非道に扱っているか、をスペイン国王に報告したものです。
教育開発との相性の悪さ
ただ、イリッチさんもすべての学校がダメだ、と言っているわけではなく、「学び」の場として学校のような空間が必要である場合もある、ことは認めています。しかし、それ以外の学びの機会も学校以上に重要であり、「先生と生徒」という硬直的な関係、「専門家と素人」という分断と特権化が意味のある学びを妨げる、と主張しているようです。そして何よりも、国家権力が「学校」を義務化することを敵視しており、学校からのドロップアウトが、人生の落後を意味してしまうことの暴力性も嫌っています。
とはいえ、義務教育の100%普及、初等教育就学率の向上、女子就学率の向上を掲げる「国際教育開発」に従事する人にとっては、『脱学校化』という主張は居心地の悪いものです。むしろ、教育開発の専門家のモティベーションをあげるのは俵万智さんの以下の句でしょう。
「学校」という語を甘きキャンディーのように発音するこどもたち (『チョコレート革命』1997 河出書房新社)
この句は、俵万智さんがフィリピンのスモーキーマウンテンに行ったときに詠んだ句です。日中、学校に行かずにゴミの山をあさっている子どもたちと出会い、そしてその子たちが「学校に行きたい」という気持ちを表出した時に、うっとりと「school」という言葉を発したのでしょう。かつて教師であった俵万智さんはその時に、日本で「学校に生きた行くない」という子供たちの発音する「学校」という言葉との違いを感じたのかもしれません。これは文明開化期に、幼い弟・妹の子守をしなければいけないために学校に行けなかった子ども達が抱いていた学校への「あこがれ」にも通じるかもしれません。これもまた、近代的装置としての「学校化」のメカニズムが作動する流れにぴったりと収まっていますね。
【2021/9/14 日本の経験 開発社会学】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー