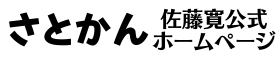明治期の美術コレクター

ミネアポリス美術館所蔵の日本絵画
サントリー美術館で開催されていた「ミネアポリス美術館:日本絵画の名品」展に行く機会がありました。室町時代から明治維新期までの日本の絵画の流れを代表する名品を見ることが出来る、コンパクトかつ分かりやすい展示で、見ごたえがありました。
こうした展覧会も、私は開発社会学の視点から見てしまうのですが、その意味では図録の冒頭にあるミネアポリス美術館の日本・朝鮮美術学芸部長のアンドレア・マークス氏の解説が非常に興味深かったです。同氏は今回日本に「里帰り」した92点の作品がどのようにしてアメリカの中西部ミネソタ州(五大湖に面した内陸州で、もともとは穀物生産から開けた州ですね)のミネアポリス美術館のコレクションに加えられたのかを解説してくれています。(アンドレア・マークス「ミネアポリス美術館の日本美術コレクション」『ミネアポリス美術館日本絵画の名品・公式図録』読売新聞社2021 pp.12-17)
同氏によると、コレクションのほとんどはもともと米国人のビジネスマン、収集家の個人的なレクションで、それがミネアポリス美術館(1883年設立)に寄贈されることで今日に至ったものだそうです。この結果、現在同美術館が所蔵する日本美術作品は9500点近くとなり、日本美術に関しては全米トップ4のコレクションとなっている、と自賛しています。
幕末から明治期にかけて、鎖国を解いて世界とつながりを持ち始めた日本には当時、欧米の好奇心旺盛なビジネスマンや美術商が次から次へと訪れ、当時まだまだ貧乏だった日本人からに二束三文で様々な美術品を買い漁っていたのでしょう。当の日本人にしても、これまで大切にしていた美術品が「文明開化」の名のもとに、西洋の「舶来品」よりも見劣りのするものとなったので、値打ちがないものとして処分したのかもしれません。また、明治政府の「大日本帝国」づくりのための「廃仏毀釈」で仏教が迫害され、仏教寺院の経営が成り立たなくなったこともその背景にあるでしょう(実は21世紀の現在、人口減少(檀家の消失)で経営が立ち行かなくなった地方の寺院が全く同じ状況に陥っています)。
これは、ある意味で美術品をめぐる植民地と宗主国の関係と似ています。ヨーロッパ各国の国立美術館には、それらの国が植民地化していたアジア・アフリカ地域の伝統美術・工芸の代表作が収蔵されています。経済力、軍事力を背景に欧米先進国が「国宝級」の美術品を「収奪」していく、という構図です。その典型例が大英博物館ですね。口の悪い人は「大泥棒博物館」とも呼びます。興味深いのは、今日これらの美術館から美術品をもともとの国へ「返還」する動きがあることですが、これはまた別の機会に考えましょう。
西洋美術の影響
美術は文明の一つの表象で、特に王朝文化が栄えたところでは王家をパトロンとする芸術家の活動が促され、生活の憂いなく創作活動に専念できることでより洗練された作品が蓄積されていきます。
世界各地にはそれぞれの地域の芸術スタイルがあるわけですが、18世紀以降西欧諸国が世界を植民地化することで、西洋美術の「グローバリゼーション」が始まります。そして多くの場合、宗主国に留学した植民地現地のエリートを入り口として西洋美術が非西洋諸国に浸透していくのですが、日本の場合は逆に、浮世絵がフランスの美術界に影響を与えたことはよく知られていますね。その意味で、日本の美術は当時の世界にあって他の途上国とはやや異なるまなざしを受けていたかもしれません。
とはいえ、明治維新期の日本の画家も多くがフランス(パリはグローバルな芸術の都でしたから)に留学し、西洋美術を身に付けて帰ることで日本の画壇にも西洋美術が浸透していきます。開発社会学の視点から興味深いのは、その西洋美術の受容のプロセスで生まれた作品群です。今回の展示で脚光を浴びていたのは青木年雄(1854-1912)の《鐘馗鬼どもの図》(図録p.184)でした。大きな画面に様々な登場人物が配置され、それぞれの表情を見せているのは明らかに西洋画の構図ですが、登場人物は中国に起源をもつ「鐘馗様」であり、日本の民間伝承に登場する「鬼」達で、彼らの表情には浮世絵画家河鍋暁斎、狩野派の逸見一信の画風を感じさせる、と図録の解説は指摘しています(p.211)。この青木年雄は、1880年代(明治十年代)にアメリカ西海岸にわたった「移民画家」だそうですが、これも伝統美術が西洋美術を受容していく過渡期の作品として見ると非常に面白いですね。
この「モチーフを日本に求めつつ、画法は西洋のものを取り入れる」、というのが明治期~大正期の日本の画壇の一つの特質だったのではないかと思いますが、その中でかねて私が気になっているのは、倉敷の大原美術館に所蔵されている児島虎次郎 (1881〜1929)の《里の水車》(1906)です。児島は明治期の日本の印象派の代表とされていますが、倉敷紡績の大原孫三郎社長の意を受けて大原美術館のコレクションのために欧州で美術品を買い集めた人でもあります。つまり、西洋画の輸入に努めたコレクターでもあったわけですね。
《里の水車》は、日本の田舎(児島の故郷の岡山でしょうか)の水車小屋の中で、母親が赤ん坊に乳をやり、その隣に手ぬぐいをかぶった娘(赤ん坊の姉でしょうか)が疲れを休めるように座っているという絵です。なんのドラマもないのですが、当時の日本の典型的な農村風景を、例えばミレーの《落穂ひろい》のような雰囲気で描いています。これはそれまでの日本画にはなかったモチーフではないかと思います。
生活の近代化と美術の近代化
後期近代/後期資本主義とも言われる21世紀の今日、地域に固有の美術やエンターテイメントは観光資源としては生きながらえていますが、決してローカルでの意味以上の価値を与えられていません。インドネシアのバリ島で毎晩観光客を相手に民族衣装(と言っても腰巻と鉢巻ですが)でケチャ・ダンスを踊る若者も、昼間はおそらくグローバル資本主義企業のブランド服や電子機器を身に付けて、西洋音楽を聴いていることでしょう。地域に固有の芸術は、グローバル経済の中心地で生み出される「近代」芸術の影響力の前にほとんど力を失っています。というのも、美術を受容する我々が既に地域固有の文脈から切り離されつつあるからです。
例えば先程の青木年雄の絵でも、「鐘馗」がなんだかわからない日本人にとっては、絵の意味は外国人が見る場合とほとんど変わりません。鐘馗様なんて、今の日本人の日常生活とほとんど接点を持っていませんね。鐘馗はもともと中国に起源をもつ道教系のキャラクターで、悪事や疫病(疱瘡など)を退治する、あるいは学業成就を守護すると信じられたことから、今でも五月の端午の節句の時に登場することはあります。疱瘡(天然痘)がワクチン接種という近代医学によって撲滅された結果、鐘馗の出番が無くなったともいえるかもしれません。
美術は作り手だけでは成り立たず、受け手がいなければ持続可能ではありません。この受け手をあの手この手で作り出すのが今日のグローバル・エンターテイメントですが、ローカルな美術はグローバル企業の視野には入りにくいものです。和服を自分で着ることが出来ないほど「近代化」されてしまった日本人にとっては、室町時代の襖絵のすばらしさを堪能するまなざしは、もしかすると日本文化に興味を持つスウェーデン人のまなざしには及ばないかもしれません。しかし、これでは「わかる人にしかわからない」という美術のスノッブ化・特権化に結びついてしまうかもしれません。
もっとも、室町時代の襖絵も当時の農民にとっては見たことも聞いたこともないもので、貴族・武士階級の人たちだけのものだった可能性はあります。美術を庶民化したのは間違いなく浮世絵ですから、この意味では江戸時代の日本は今日の資本主義的美術市場を最初に開拓したとも言えますね。
いずれにせよ、途上国の近代化に伴ってそれぞれの地域がもともと持っていた美術文化がどのように変化しているのかは、とても興味深いテーマなのです。
【日本の近代化 2020/6/24】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー