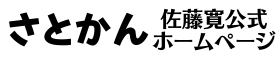女性画コレクター福富太郎
東京ステーションギャラリー
先月(2021年6月)末まで東京ステーションギャラリーで開催されていた「福富太郎の眼」展を見に行きました。先日のミネアポリス美術館の日本画展(サントリー美術館)に続いて、江戸から明治への文明開化(近代化)の時代に、日本人の「女性の描き方」がどのように変化したのかを見る機会となったので、面白かったです。
会場の東京ステーションギャラリーそれ自体も、日本の近代化とは無縁ではありません。東京駅舎は辰野金吾(1854:嘉永7~1919:大正8)の設計により1914(大正3)年に建てられた鉄骨レンガ造りで、第二次世界大戦中の空襲で一部が失われていたままだったそうです。2012年の改修でオリジナルの三階建てが復活したもので、その駅舎の中にギャラリーがあります。内装にレンガが露出したりしてそれなりに雰囲気のあるギャラリーです。レンガを用いた意匠は当時の最先端建築であり、日本が「西洋並み」になろうと必死だったころの遺産とも言えますね。辰野は、1873年に現在の東大工学部の前身である工部省工学寮に入学、その後1877年にお雇い外国人としてイギリス人のジョサイア・コンドル(1852-1920)が教授として来日し、彼の薫陶を受けます。コンドルは鹿鳴館やニコライ堂を設計したことで有名ですね。
昭和のキャバレー王
福富太郎(1931-2018)は、日本経済が東京オリンピック(1964:昭和39)に向かう高度成長期の波に乗って全国にキャバレーを展開し「昭和のキャバレー王」と言われた実業家です。1960~70年代のテレビ最盛期にはワイドショーでコメンテーターや「人生相談」などをする、時代の寵児だったようです。彼は、事業に成功することで一種の成金になりますが、そのお金を日本の「美人画」のコレクションに投じるのです。「美しさ」を売る多くの女性を雇用する経営者が、「美人画」を好むというのはなんとなくありそうな話ではありますが、福富のすごさはその「目利き」力にあるようです。
1人の人が自分の趣味で蒐集した「コレクション」は、その作品群自体が一つの作品となることを今回の展覧会はよく示していました。福富のコレクションは鏑木清方(かぶらき・きよかた:1878:明治11-1972:昭和47)の作品から始まっています(今回の展示構成も鏑木清方から始まります)。鏑木については明治から昭和にかけての「浮世絵師・日本画家」という説明がウィキペディアにあります。まさに、江戸期の浮世絵の伝統を継承しつつ、近代化する日本の中で新たに登場した「日本画」というジャンルを生きた人のようです。福富は清方の絵を入り口として、その周辺の浮世絵、日本画家の作品にも手を広げ、洋画家の描く日本女性もコレクションの対象となっていきます。
江戸の世界と鹿鳴館の世界
展示室の最初に掲げられていたのは清方の「あしわけ舟」(1904:明治37)という絵で、鹿鳴館のダンスホールに入ろうとする洋装した日本女性たちの様子を描いています。私は、日本の近代化についてのレクチャーを「鹿鳴館」から始めることが多いのですが、レクチャーの参考資料にできるような、鹿鳴館に集う日本人を描いた絵はあまり多くないのです。よく使うのはジョルジュ・ビゴーのポンチ絵か、浮世絵師である楊洲周延の『貴顕舞踏の略図』なのですが、この「あしわけ舟」は一人一人の洋装のディーテールも見えて「使える」と思いました。
こうした「文明開化」期の風俗も題材にしてはいますが、清方は基本的には浮世絵師で、題材は江戸の庶民社会にとっており、ストーリー性のある題材は近松門左衛門などの作品世界に近いものが多いようです。「薄雪」(1917:大正6)は、近松の作品『冥途の飛脚』の一場面から取っており、主人公である遊女梅川と忠兵衛が心中する場面を描いたものだそうです。浄瑠璃で演じられるときは、太夫(三味線に合わせてセリフを言う人)が、心中直前の二人の心情を「大門口の薄雪も今降る雪も変らねど変り果てたる我が身の行方」とうたい上げるところで、タイトルの「薄雪」はこれから来ているとのこと。
開発社会学に面白かったのは、明治期の寄席の様子を描いた「京橋・金沢亭」(1935:昭和10)で、畳敷きの二階の広間に、たばこ盆と座布団が並んでおり(当然まだ椅子席ではありません)、ご隠居さん風の人や、職人風の男、粋な「おかみさん」の二人連れ、小僧さんなどの人物が描かれていて、江戸期以来の「大衆芸能」のあり方が伝わってきます。軒先の看板に「人情ばなし・三遊亭圓朝」の看板が見えるところも臨場感があります。圓朝(1839:天保10-1900:明治33)は、人情噺の名人と言われ、近代落語界の元祖ともいえる人です。
同じように「風俗画」として興味深かったのは、池田輝方(1883:明治16-1921:大正10)の「幕間」(1915:大正4)で、これは歌舞伎座の休憩時間の賑わいを江戸時代と明治時代の二つの絵で対比しているものです。会場の解説によれば右側が江戸期で、大奥の御殿女中たちが歌舞伎を見に来ている様子だそうです。左側は明治で、もちろん描かれている女性たちはみな華やかな和服姿ですが、こちらはコンパクトのようなものでお化粧直しをしているところや、売店でお土産物を選んでいるところなど、今日の歌舞伎座の幕間にも通じる光景がみられることが興味深いです。
絵画の大衆化と古典化
清方以外の多くの作家による美人画もコレクションしていますが、いくつかは当時の小説、新聞連載小説の挿絵として書かれたものだそうです。日本の近代の特質の一つに、初等教育の急速な普及に伴い識字率が高まり、庶民も新聞を読むことが出来た(もっともそれを毎日講読するほどのお金があるかどうかは別ですが)ことがあります。「新聞小説を読む」という娯楽も新聞の講読者数増加に一定の貢献をしたと考えられますが、これに挿絵があることで読者の理解を容易にしたのではないでしょうか。これはまた、それまで限られた人にしか見ることが出来なかった絵画の大衆化にも寄与したのかもしれません。
伊藤小坡の「つづきもの」(1916:大正5)は、若い女性が台所仕事の合間に、新聞の連載小説を真剣に読みふけっている風景です。これも解説によれば、女性の頭の上に掛かっている柱ごよみの日付は八日ですが、新聞の日付は九日とのことで、新聞が届いたら日めくり暦をめくるよりも先に連載小説に取り掛かった、ということを示しているのかもしれません。
小説の挿絵とは別に、洋画の影響を受けて作成された女性画ももちろん含まれていますが、昭和初期までの作品がほとんどなので服装は基本的に和服です。和服に日常的に接していたころの人びとに比べると、ほとんど和服を目にしない現代に生きる我々の「和装の女性」に対する審美眼は鈍っているのだと思います。また、画材になっている物語に対する知識も失われると、絵画から受け取るメッセージも貧弱になってしまうかもしれません。北野恒富「道行」(1913:大正2)は、近松の「心中天網島」の心中への道行き場面が題材ですが、それを踏まえて見ると一層、女性の虚ろな目のすごみが感じられるかもしれません。この意味で、福富コレクションは「古典」になりつつあるのかもしれません。せっかく大衆化した絵画が、文化的・風俗的な変化によって「古典」化してしまう、というのはやや寂しいですね。
今日の途上国でも同じことが起こりつつあります。伝統的な文化や風俗が、近代化とともに失われていき、親の世代には感覚的に理解できた背景が、子供の世代に受け継がれなくなり、孫の代には「異文化」になる。もったいない、というのはよそ者の視点であり、当人たちはより良い生活を求めていくのに精いっぱい。高度成長期にそうした変化を感じ取っていたからこそ、福富太郎は変化していく日本画それも女性画を蒐集することを通して、世代と世代を「繋ぎとめよう」としていたのかもしれません。
さとかん【2021/7/4 日本の近代化】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー