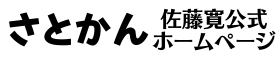【もし今漱石がロンドンにいたら・7】《カワイイ》
近代日本が、富国強兵・殖産興業・和魂洋才で必死に西洋に追いつこうとしていたときに、すでに西洋で一定の評価を得ていた「日本」は《浮世絵》に代表される絵画でした。
漱石の留学時代は、「西洋型国民国家」をモデルにした明治日本が、西洋諸国との「不平等条約」を改正してもらうために「遅れた」国状態から一刻も早く抜け出そうともがいていた時代でした。そして漱石はロンドンで、西洋と日本の「開化」の性質の本質的な違いを認識し、にもかかわらずその懸隔を「上滑り」ながら必死に埋めなければならないとあえぐ祖国の姿に心を痛めていたのです。
しかし、そのときすでに芸術の世界では、先進地域西洋においても「日本」は明確に評価されていました。いわゆる「ジャポニズム」の流行です。 ジャポニズムは19世紀末から20世紀初頭にかけて主としてフランスを中心に注目を集めた一連の動きで、浮世絵が西洋絵画に影響を与えたのみならず、工芸や建築、演劇、さらにはファッションなどにも影響を及ぼしたようです。この事実を見ると、単なる異国情緒の「オリエンタリズム」とは異なり、深い理解に基づく評価がなされていたようです。もし漱石がフランスに留学していたら、ノイローゼにならずにすんだかもしれませんね。
私も、たとえば浮世絵がゴッホに影響を与えたとか、印象派の流れの基礎になったとかという話は素人ながら聞きかじったことがありました。芸術は政治・経済パワーバランスの外にあるために、単線論的な「先進-後進」構図から自由な視点で評価することが容易だということなのでしょう。でも、そうした評価があったとしても、漱石の「近代化」を巡る悩みは本質的には解決しません。この意味で、私の中では「ジャポニズム」と「非西欧世界の近代化」とはまだうまく折り合っていません。
さて、2010年の冬から2011年の春にかけてロンドン・バービカンセンターで開催された展覧会のタイトルは「Future Beauty」。そして副題が「30 Years of Japanese Fashion」。なぜ「30年」なのか私には謎でしたが。芝居「Shun-kin(春琴)」とコスプレショーを見て、私のこれまでの「日本の表象の仕方」観が動揺を始めたので、余勢を駆って翌週、展覧会の方も見に行くことにしました。
会場には三宅一生、山本耀司、川久保玲という三人のファッションデザイナーの作品が主に展示されており、展覧会のメイン・コンセプトは日本の文化を背景にしつつも、伝統的な日本にこだわるのではなくインターナショナルに通用するファッションを提案した三宅一生が出現してからの30年を振り返り、これからの方向性を占う、ということのようでした。
本来洋服と和服の発想は根本的に異なり、立体裁断の洋服に対して和服は平面の組み合わせで身体を覆うシルエットを大切にするそうで、それを洋服に持ち込んだところがこれら三人の「インパクト」だったということのようです。
展示の最後には原宿のストリート・ファッションが展示してあり、「カワイイ」コスプレも含めた「クールジャパン」で締めくくってありました。前週に引き続き私は、こんな風に日本を表象するやり方があるのだ、という新鮮な驚きを覚えました。とはいえ、日本のファッションデザイナーのデザインと「カワイイ」がどのような関係にあるのかは、今ひとつ腑に落ちませんでした。
この 「Future Beauty」の会期が終わって一月ほどたった頃、企画者(curator)である深井晃子さんの講演会がロンドンでありました。その場でこの展覧会の意図が解説され、いろいろな疑問が解けました。彼女によれば、30年前に西洋に登場した日本人デザイナーたちのファッションは、シルエット(影)を大事にするという意味で日本的であり、それは谷崎の『陰翳礼讃』という美学(aesthetic)にも通じるというのです。それでShun-kinが上演されたのですね。
また、深井さんは日本の美学の核心として「わび」「さび」を紹介したのですが、それに加えて新たな日本的美意識として「カワイイ」を挙げたのです。そしてそれが、たとえば川久保玲のファッションに取り入れられて西洋に発信されているのだと。なるほど、これは大胆な分類です。日本に固有な伝統を明示的に表現するのではなく、洋服ファッションというジャンルの中に「日本」が潜在するという点で、Japanese Fashionは、明らかに漱石の生きた時代のジャポニズムとは異なるのです。
「カワイイ」は文明開化の「ざん切り頭」同様、軽佻浮薄に見えるかもしれません。しかし、それを日本文化の文脈の中に置き、非西欧社会の近代化モデルの「奇形」としてではなく「独自の進化」として評価するというのは、漱石には思いつきもしなかった視点かもしれません。神経衰弱になっていた漱石が、この視点を知ったなら、膝を打って快哉を叫んだのではないかと思います。【2011/6/23】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー