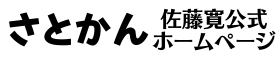【ブライトン特急・26】《Admission Free》
***50回連載目標の半分まで来ました。ネタ切れにならないか心配ですが、あと少なくとも25回は続けてみたいと思います。すでにお気づきの方もいると思いますが、毎日の「英単語」はアルファベット順に選んでいます。今日から再びAに戻ります。***
ロンドンに限らず、イギリスの博物館、美術館は「入場無料」(Admission Free)のところが多いです。世界の博物館ともいえる大英博物館もこの例に漏れません。巨大な施設を維持するのに「入場無料」でどうしてやっていけるのでしょうか。
資金源はいくつかあり得ます。一つは公共予算。国や地方自治体の予算で職員などの経費をまかなっている施設も多いと思います。ロンドンの大英博物館、マンチェスターの科学産業博物館などはこの例でしょう。大英帝国の威信をかけた国家的事業です。
二つ目は「財団」(trust)。博物館や美術家の中には貴族や大金持ちが個人的に集めたコレクションをもとに開設されたものも少なくありません。しかし、蒐集家であった人が亡くなったあともこれを維持する意欲や能力や財力を子孫がずっと維持できることはまれです。そこでどこかの段階で、収集品を遺産とともに「財団」に寄贈し、遺産を元手に投資などで運用しながら維持費をまかなうという方法もしばしばとられているようです。これは、イギリスが「身分社会」で貧富の差が激しかったからこそ可能になった形態といえるでしょう。
三つ目の資金源として「多国籍企業」「優良企業」の隆盛に伴い、特定の企業が展示の一部を全面的に支援し「スポンサー」として名前を出すこともあります。イギリス近代美術コレクションで知られる「テートブリテン」の今年の企画展を多国籍企業BPがサポートしていました。企業から見れば、これは企業の慈善活動(philanthropy)の一部です。
四つ目は一般の人々からの「寄付」(Donation)です。ほとんどの博物館・美術館は入場無料ですが、必ず入り口に「寄付金入れ」があります。また、「友の会」会員になってもらい、いろいろなイベントに招待される特権と引き替えに会費を募るという方法も一般的です。さらにかつての貴族や資産家の「遺産」(Legacy)を財団の基金に寄付することも行われています。
五つ目は「シッョプ」の利益です。ある程度の規模の博物館・図書館にはその施設の「お土産・特注グッズ」を売る売店や、カフェなどがあり、そこからの収益も多少は維持管理費に回るでしょう。これは、日本でも行われていますね。
もちろん中には、経営の苦しい博物館・美術館もあるでしょうが、人気のあるところはおおむねこの入場無料の建前で運営しています。これには、イギリスに寄付の風習が根強くあることが貢献しているように思います。ざっくり言えば「貧乏人は出さなくて良い」が「金がある人は相応の負担をしなさい」という社会規範です。これもまた、有産階級と無産階級がはっきり分かれている、身分制が未だに色濃く残っている、職業によって給与水準が天地ほども違う、という「不平等社会」だから成り立つ仕組みです。とはいえ、芸術・文化の維持には欠かせない規範かもしれません。
ところで「金のある人は相応に出す」ということは、一つのサービス(展示品の鑑賞)に対して、異なる料金を払う「一物多価」のシステムです。近代的な商品市場はデパートなどの「定価販売」のように、通常「一物一価」が原則ですね。もっとも最近では、デパートも「会員様ご優待」という「一物多価」システムを取り入れていますが、これはたくさん買う財力のあるお得意様が得をする仕組みです。
これに対して「金のある人は相応に出す」というのは、財力のある個人が自発的に「損をする」ことを期待するという点で180度異なります。経済的には何一つ得になることはないのです。もちろん、寄付者名簿に名前が載る程度のメリットはあってもたかがしれています。こんな不可思議な原則が資本主義市場の発祥地イギリスでいまだに機能していること自体が興味深いですね。
そしてお金がない人は、寄付をせず、ショップでも買い物をせず、カフェにも寄らずに鑑賞だけして帰ることが出来ます。それそがAdmission Freeの原則、つまり「身分貴賤の隔てなく、芸術や知識にアクセスできるべき」という精神なのです。もちろん、金持ちでも払いたくなければ一文も払わなくても文句は言われません。個人の良心に任されているのです。2009年の大英博物館の入場者数は560万人だそうで、もしも入場者一人あたり5£(700円)でも取れば、2800万ポンド(40億円弱)の収入になる計算ですが、そんなことはしないのです。これは「文明国の風格」と言うにふさわしい態度といえましょう。
ところで、お金のある人だけが相応に払う、という価格体系は実は現在、途上国の社会的ビジネス(Social Business)で注目されています。これをクロスサブシデイー(Cross Subsidy)といいますが、たとえばインドで社会起業家がやっている都市の救急車サービス(公共の救急車は頼りにならないので民間のサービスが求められてます)は、お金のある人からは多めに料金を取りますが、貧乏人からは料金を取りません。この結果、貧乏な人でも救急医療にアクセスが可能になり、救える命が増えるのです。また、やはりインドで心臓手術を専門に行うナラヤナ・ヒュルダヤラヤ社は、患者の収入に応じて異なる手術料金を請求し、最貧困層は無料で手術が受けられるようにすることで、貧困層の命を救っています(UNDP『世界とつながるビジネス』)。
クロスサブシディーの仕組みは、金持ちが貧乏人の分まで払うことによって成り立っています(つまり、消費者間の補助金ですね)。これは通常の市場原理からは逸脱した行為ですが、「世の中は持ちつ持たれつ」という世界観の中にあれば、特に不思議なシステムではないのかもしれません。
【2011/6/15】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー