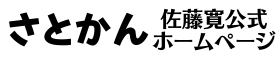【もし今漱石がロンドンにいたら・4】《黒澤映画》
私は日本ではあまり映画を見ないのですが、こちらに来てクロサワ映画を二度見に行きました。日本映画をイギリス人がどのように見ているのかを知りたかったからです。
一度目は、ロンドンから列車で2時間ばかり南に行ったチチェスターという小さな町の公共映画館で『生きる(1952年作品)』を見ました。南イングランドはそもそもローマ人がイギリスを占領したときの根拠地になったところなのでローマ時代からの町もいくつかあり、チチェスターもその一つです。町の真ん中に大きなカテドラルがあり、その横にとても手入れの行き届いた美しい庭園があります。かつては、この教会を中心にして市壁に囲まれていたようで、所々に市壁の跡が残る、こじんまりとして品のある町です。
さてこの町では、町民ホールのような建物の中に小さな映画館もついていて、世界中の名画を上映しているのです。あるとき何かの拍子にここで「生きる」を上映するということを知り、サセックス大学のあるブライトンから列車で海沿いに一時間弱西に向かってたどり着きました。旧市壁の外側に面した緑豊かな公園の中に映画館はあり、定員104人の席に20人くらいの観客で、日本人は私のみ。あとは地元の品の良さそうな中年以上のイギリス人です。
『生きる』は第二次世界大戦後、高度成長前の日本の都市を舞台にしているので開発研究者としての私にとっては映像資料的にも興味深いのですが、それはさておきメルヘン・ドキュメンタリー的なストーリーはわかりやすく、また主人公が夜の町を飲み歩くシーン(キャバレー、ダンスクラブなど)はまさに「西洋かぶれ」的な設定が多くて、イギリス人にも違和感なく理解できるでしょう(最初は居酒屋から始まるのですが)。観客は最後まで、じっくりと見てそれなりに満足そうに帰って行きました。特にエキゾチズムを感じるでもなく「名画」として堪能していた、という感じです。もちろん、みなさんクロサワが何者であるかは十分に予備知識が備わっている風でした。
2度目は『七人の侍(1954年作品)』で、これはロンドンの一大カルチャーセンター「バービカン」のシネマで見ました。このときは大きなスクリーンで、観客も100人ほどはいたと思います。場所柄こちらに住んでいる日本人が1/3ほど、残りは日本に行ったことがある、日本に興味があるという風なイギリス人が多かったように思います。アフリカ系の人はほんの少し。
筋は単純バトルストーリーですから問題ありませんが、英語字幕で三時間半にわたる大作ですから、結構疲れると思うのですが皆さん最後まで飽きずについてきてました。また舞台設定は中世の日本ですから着ているものや風景にエキゾチズムはあるのですが、この作品はこのあと西部劇に翻案されたり、宇宙ものに翻案されたりと多くの欧米の映画に「模倣」されたくらいですので、服装や風景は筋立て理解の妨げにはならないのでしょう。これまた予備知識のある人は十分に楽しめたという感じです。
つまり「クロサワ」がどこの国の人であるかには関係なく、イギリスの映画好きの人たちの中には「常識」の一部として受け入れられ、咀嚼されているのだ、ということがよくわかりました。
さて、では漱石が今イギリスにいてこの状況を見たらどう考えるでしょう。まず、映画が発明されたのは1888年、日本にこれが紹介されたのが1896年ですから、「活動写真」というものの存在にはもちろん漱石は気づいていたでしょう。1897年には日本でも輸入映画の興行が始まっており、国産映画も1899(明治32)年には最初のものが出来ています。これは漱石の英国留学の一年前です。漱石が英国留学中にイギリスで映画を見た形跡はありませんが、帰国後は落語・講談好きの漱石ですから、もしかしたら一度くらいは日本で見たかもしれませんね。
漱石の言う「上滑りの開化」のなかに、こうした西洋起源の活動写真を使った娯楽が含まれていたかどうか、私には興味深いテーマです。確かに技術的には西洋起源ですが、最初の国産映画は『芸者の手踊り』を実写し、歌舞伎座で上映したものだそうです。完全に伝統芸能の世界ですね。最初のストーリーもの映画は同じ明治32年に封切られた『ピストル強盗清水定吉』で、日本で最初の拳銃事件を題材にしたものでした(このあたり、ウィキペディア情報に基づいています)。
こうしてみると、日本の映画産業は当初から、西洋の技術を用いて国産のコンテンツを作るという「ハイブリッド」の萌芽が見られるのではないでしょうか。また世間を賑わした事件を題材にして芝居にするというのは、近松門左衛門が得意とした手法ですから、従来の日本の興業文化とも連続性がありますね。
映画の場合は日本が開国した後に西洋で発明されているのでキャッチアップが容易だったこと、ソフト産業なので日本の国情にあったコンテンツ作ることが出来たことなどもあり、漱石の言葉で言えば「内発的な開化」の道筋をたどった例と言えるかもしれません。
漱石の小説にあんまり映画が出てこないところをみると、自身は好きではなかったのかもしれませんが、漱石は時代劇は好きだったようなので『七人の侍』がその後西洋の映画監督のお手本になった、という事実にはまんざらではない、という顔をするのではないかと思います。【2011/6/15】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー