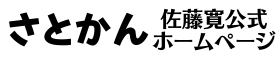【ブライトン特急・30】《Ethical Consumer》
私の現在の研究テーマの一つは倫理的貿易(Ethical trade)です。この言葉を聞いたとたんに「うさんくさい」と思ったあなた・・・・それが普通です。とくに日本語で「倫理」と言うとなんだかよそよそしい、実生活とかけ離れたニュアンスがありますよね。でも、イギリスではEthics/Ethicalにはもう少し違ったニュアンスがあるように思います。
こちらに来て初めて知ったのですが、マンチェスターに本拠を置く『倫理的消費者(Ethical Consumer)』というなかなか面白い雑誌があります。基本的には消費者啓蒙のためのもので、有力な企業がどの程度「倫理的か」を毎号様々な視点から精査し、ランキングをつけて発表するのです。日本で戦後、商品テストを実施して一世を風靡した『暮らしの手帖』と同じような発想かもしれませんね。
1989年に当時マンチェスター大学の学生だった三人が創刊し、隔月ながらもう20年以上続いています。発行部数は紙媒体で5000部程度、インターネット版もあります。三人の関心は別々で、一人は社会正義に関心があり企業活動における労働搾取などを、二人目は企業活動の環境破壊を、三人目は動物愛護の観点から企業の商品開発における動物実験をそれぞれ「非倫理的」と考え、これらの活動をやめさせるために雑誌を創刊したのです。
なぜなら、20代の若者がいかに正義感に溢れていても直接企業に影響力を与えるには不十分です。そこで、彼らは企業の「非倫理的行為」を指摘し、人々にボイコットを訴えるという戦略を取りました。その最初の成果がアパルトヘイトの南アフリカからのバークレー銀行(イギリスの大手銀行です)の撤退だったそうです。
この成功を基礎に『エシカルコンシューマー』誌は、自分たちの独自調査結果を雑誌に公表して人々に訴え、かつ企業に圧力をかけるという路線を歩んでいます。マンチェスター起源でリベラルな全国紙である『ガーディアン』紙の支援もあり、今では大手のNGOとの連携も確立、企業からの関心も高まっているようです。現在では各企業のCSR(企業の社会的責任)活動評価、環境インパクト評価なども行っています。時には企業から取引企業の活動の倫理性に関するリスク・スクリーニングを頼まれることもあるようです(こうしたコンサルタント調査も重要な収益源です)。
さてこのボイコットという戦略、欧米の消費者運動ではしばしば用いられます。特に途上国問題に関心を持つキャンペーン組織は、意図的に大衆市場に攻勢をしかけ、政治的消費(Political consumption)を通してグローバル企業に圧力をかけようとしています。こうした戦略を”name and shame”(名指しで恥をかかせる)戦略と呼びますが、その代表的な標的は粉ミルク販売促進で途上国の赤ん坊の死亡率を高めたと批判されたネスレですね。
ネスレに限らず欧米の多くの多国籍企業は過去30年くらいの間に多かれ少なかれこうしたキャンペーンの対象になったことがあります。サッカーボール生産の労働条件でボイコットされたナイキ、コーヒー買い付けで批判されたスターバックスなど、業種も多岐にわたっています。イギリスでは特に服飾関係の小売業(プライマークやマークス&スペンサーなど)がボイコットの標的になりやすく、「児童労働」というニュースがあると、消費者は一気に去ってしまうのでこうした「風評被害」を強く恐れています。そして消費者がこうした圧力をかける時の武器が「倫理性」なのです。
エシカルコンシューマーの編集長ロブさんは、イギリスで倫理的消費者運動が高まったのは、1970年代末からのサッチャー政権の「功績」だと言います。つまり、政府がこうした規制を担う役割を放棄した結果、市民の間に「自分たちが企業の倫理性を監視しなければならいない」という危機感が生まれた結果、倫理的消費者層が増えたというのです。こうした動きを彼は市民による規制(Citizen Regulation)と呼んでいます。
しかし、市民には政府のような権力はありません、また多国籍企業のような資金力もありません、そんな市民が政府や企業に圧力をかける足がかりが「倫理性」なのです。つまり倫理とは何も持たない者の武器なのでしょう。ただし、こうした戦略が成立するためには、国家、企業、市民社会の間で「倫理性」が共有されていなければなりません。欧米ではその共有される価値観のベースにキリスト教があるように思います。
ただ、同じ欧米でも倫理性の訴える力点は国ごとに違うようです。イギリスの消費者は途上国での労働搾取に関心が高いのに対して、ヨーロッパでは遺伝子組み換えに対する警戒心が強く、ドイツは環境にセンシティブで、イタリアは企業の汚職に反応する。アメリカでは人種差別が強い反応を引き起こす、などです。それぞれの文化的、歴史的背景によって「倫理性」は異なるのです。ロブさんはまた、動物権(animal rights)については、ヒンズー教、仏教の思想とも通じるのでアジアで関心があるのではないか、と言っていました。
とはいえ、日本では、ボイコットはあまり一般的ではありませんね。それには企業と社会の関係性、人々の「礼儀正しさ」、正面から対立することを避けたい気持ちなどが関係していると思います。また、そうした倫理性については政府が監督してくれるという信頼もあるのかもしれません。しかし、日本の消費者は食の安全についてはかなり感度が高いし、フェアトレードなど途上国問題に関心のある消費者も増えています。そのうち『倫理的消費者』日本語版が出来る日が来るかもしれませんね。【2011/6/19】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー