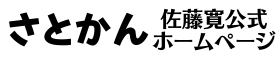【ブライトン特急・23】《Xenophobia》
ロンドンは本当に外国人が多い町なので「ロンドンはイギリスではない」という人もいるくらいです。世界中から観光客が来るばかりではなく、途上国から一攫千金を目指してやってくる移民労働者も少なくありません。この移民労働者の過剰流入はアメリカでもヨーロッパ大陸でも社会問題化していますが、イギリスは日本と同様島国なので、比較的不法流入の阻止がしやすいはずです。
ところが、今やイギリスでもこの移民労働者の抑制が大きな議論の的になっています。最大の理由は、元々のイギリス人の失業問題です。途上国や東欧から低賃金でも喜んで働く労働者が流入すればするほど、イギリス人の就職は困難になります。特に低所得、低教育の人々により大きな影響があります。2010年に発足した保守連立政権のキャメロン首相は「これまでの多文化共生政策は再考が必要だ」という発言で「イギリス人」を優先する方向を示しています。
入国管理の厳格化も唱えられていますが、特に途上国から観光ビザで到着しながら入国時に亡命(asylum)を申請する人たちも多く(ヒースロー空港の到着ロビーにはこのための案内が大書されています)、民主主義国家イギリスとしてはそうした人たちをむげに追い返すわけにもいきません。
他方、入国管理局(UK Border)の審査が生ぬる過ぎるのではないか、という批判もしばしば聞かれます。就労目的なのに、観光や学業と偽って入国する人々の摘発のために、警察などから様々な内報(tip-off)が寄せられているのに、入国管理局はこれをきちんと処理していないという批判が報じられたことがありました。また違法入国なのに強制送還せずに保護拘留し、しばらくすると結局入国が認められてしまうのでは「暗黙の恩赦」(Silent Amnesty)を認めているのと同じである、という批判も聞かれます。
こうした批判の高まりとイギリス人の失業率とは相関関係があるようです。炭鉱などの一次産業や製造業がほぼ壊滅してしまったイギリスの経済は、金融業とサービス業、そして大学業(海外から留学生が来ることによる経済効果)で成り立っています。しかし、留学生がそのまま居ついてしまえば、ホワイトカラーの職も徐々に外国人に奪われてしまうかもしれません。このため、これまで大学や大学院卒業後1-2年間自動的に与えられていた滞在ビザは今年から廃止されてしまうようです。
しかし、どれだけ流入を制限しても、日本と違ってすでに多くの「アジア系(イギリスでは多くの場合南アジア系の人々をさします)」「アフリカ系」の人々が社会に組み込まれており、三世、四世などイギリス国籍を持っている人も少なくありません。これは植民地時代の遺産であり、これらの人の存在を否定することは過去の大英帝国の栄光を否定することにもなるので、いかな愛国者でも「白人以外は出て行け」とはなかなか言えません。
こうした中で、今一番やり玉に挙げられるのが「イスラム教徒」です。近年イギリス国内で急激に増加している中東、南アジア系のイスラム教徒たちは服装も比較的目立ちますし、キリスト教をベースとするヨーロッパ人にとっては、十字軍の昔からの歴史的な仇敵意識があるようです。この「異教徒」嫌いは20世紀前半においてはユダヤ教徒に向けられていたのですが、21世紀の今日ではイスラム教徒が標的になっており、特に2001年の「9.11」以降イスラム教徒を特に標的にした外国人嫌い(xenophobia)が顕在化しているように思います。フランスで女性のブルカを禁止する法律が出来たり、ドイツでトルコ人の移民に対する排斥運動が起きたりするのも同根です。
イギリスでその尖兵となっているのが「イングランド防衛連合(English Defense League :EDL)」という団体で、イングランドからの「イスラム過激主義」の排斥を主張しています。もともとはロンドン郊外のルートンという町でサッカーファンのフーリガン(Hooligan)が母体となって誕生したようですが、路上デモなどを通じて徐々に支持者を増やしているようです。主導者は「イスラム法(シャリーア)は野蛮である」と主張しているそうです。
イギリス人の若者の失業は確かに大問題ですが、EDLのような極端な排斥主義は良識ある国民からは眉をひそめられています。しかし、これはイスラム教徒の人々にとっては生活基盤を脅かされかねない大問題で、すでにイギリスで市民権を持っている人たちも肩身の狭い思いをすることになります。
2010年10月末にカタール経由でイギリスに届いたイエメン発の航空貨物の中に爆発物が発見されるという事件がありました。このとき「アラビア半島のアルカーイダ」の犯行であるとされたため、多くの英米の国民の間では「9.11」の恐怖がよみがえり、「手遅れにならないうちにイエメン国内のアルカーイダのアジトを空爆すべき」との世論が高まっていました。ちょうどその頃王立国際問題研究所(Chatham House)でイエメン問題を巡るセミナーがありました。
私も含めてイエメン研究者は、「イエメンの安定にとってはアルカーイダはマイナーな問題であり、それよりも重要な国内問題の処理が優先されるべき」であり、「欧米諸国による空爆はむしろ国家破綻につながりかねない」ことを指摘していました。私は今でも、欧米が軍事介入を差し控えることが多くのイエメンの庶民のためになると考えています。
ところが、このとき聴衆の中にいたイエメン三世の若いイギリス人が、「イギリス国民である我々は、我々の治安の維持に血税を使ってもらいたい。もしもイエメンが我々の治安にとって脅威であるなら、空爆すべきではないか」と発言しました。
一瞬耳を疑いました。三世とはいえ、彼の外見は完全なイエメン人です。おそらく純粋なイエメン人の親から生まれ、子供の時からイギリスで教育を受けてきたのだと思います。確かに、イギリスの納税者のロジックとしては筋が通っています。しかし、それはイエメンに住んでいる、力のない人々、貧しい人々に対する配慮の一切ないロジックです。もちろん、彼にとって自分の国はイギリスで、そのイギリスで自分たちが排除されるような問題を起こす国には何のシンパシーもない、むしろ迷惑だということなのでしょう。
彼のような人には出来ればイエメンとイギリスの架け橋になってもらいたいところですが、彼にとってイエメンはすでに「異国」です。あるいは出来れば消したい「烙印」なのかもしれません。これは悲しい現実です。
外国人嫌いがはびこればはびこるほど、マイノリティーは自分の生存維持のために、互いに傷つけあうことになりかねません。大英帝国の遺産は、これからもまだまだこの国に重くのしかかり続けるでしょう。【2011/6/12】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー