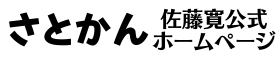【もし今漱石がロンドンにいたら・9】《蝶々夫人》
私は日本にいるときはあまり観劇に行きませんが、ロンドンでは様々な演目が比較的安価で見られることもあり週末にはよく劇場に通います。漱石も留学中に演劇やリサイタルに何度か足を運んだようなので、その足跡を追体験する目的もあります。
ロンドン漱石記念館に記録されている漱石の観劇先はHer Majesty’s TheatreとRoyal Theatre Hey marketです。どちらもロンドンの中心、トラファルガー広場近くにあります。前者では現在25年のロングランミュージカル『オペラ座の怪人』を上演中なのでロンドンに来て最初に見に行きました。後者では定期的にドラマ(演劇)が上演されており、第一次世界大戦中の英国空軍基地を舞台にした『フレア・パス』という芝居を先日見に行きました。この劇場のアッパー・サークル席への階段はいまだに木の床で、踊り場には手回し式の電話が鎮座しており、漱石が来た頃もこうした雰囲気だったのかなあ、と思わせるものがありました。
さて、今年(2011年)3月生まれて初めてオペラを見る機会がありしまた。演目は『蝶々夫人(Madam Butterfly)』です。これは、途上国研究の視点からは面白いテーマのオペラです。19世紀後半、近代化を始めたばかりの後進国日本に、先進国アメリカから海軍士官がやってきて長崎に駐在します。そして日本人のエージェント(女衒ですね)を仲立ちにしてめとった現地妻が「蝶々さん(Cio-Cio-San)」です。この時代にはこうした取引の倫理性はつゆほども話題にならなかったでしょう。21世紀の今日でも途上国では似たようなことが(もう少しオブラートに包まれた形で)行われているかもしれません。
このプッチーニによる戯曲は1904年にイタリアで初演されています。漱石が英国留学から帰国した2年後で、『倫敦塔(1905年発表)』を執筆中であった頃かもしれません。いずれにせよ当時のヨーロッパの日本観にはまだまだ異国趣味のイメージが色濃くつきまとっており、これもそうした時代を反映した作品です。
さて、蝶々さんはピンカートンの子をもうけたものの、任期を終えたピンカートンは本国に帰ってしまいます。まあ端的に言えば、捨てられるわけですね。そうは知らない蝶々夫人は「ピンカートン様」の帰りを待ちわびるのですが、数年後にピンカートンはアメリカ人の妻を帯同して新婚旅行かたがたやって来ます。そして自分の子がいることを知り、「この子を引き取って育てる」と申し出るわけです。子供にとってはそれが最も望ましい(先進国で教育を受けることが出来るのですから)だろうという善意です。アメリカ人の側から見れば新婦の心の広さが賞賛される設定でしょう。
漱石はこのストーリー、好きじゃなかったのではないかと思います。西洋における「日本」の不在、日本に対してしかるべき敬意が払われていないこと、をまさに一人の女性の悲劇が表象しているからです。そして、その舞台や衣装の表現のされ方は多分に「オリエンタリズム(異国趣味)」的であり、日本に対する真の理解が欠けている、と憤ったのではないでしょうか。まさに、漱石のノイローゼを増長するネタでしょう。
しかし同時に、西洋近代の芸術形態であるオペラの題材に日本が選ばれ、しかもこの作品が西洋の人々の喝采を博してオペラの定番になったことも、また他面の真実です。初演の1904年は日露戦争が始まった年でもあり、翌1905年には日本海開戦で日本がロシアを破り、西洋世界に衝撃を与えることになるという意味で、「西洋における日本」の位置づけは変わりつつあったのです。
今回のロイヤル・アルバート・ホールでの上演用のプログラムには面白い解説がありました。曰く、「1904年2月のミラノでの初演の失敗を受けて改良された『蝶々夫人』が出直し初演されたのは1904年5月28日で、そのちょうど一年後(1905年5月27日)には、イギリスによって訓練された日本の海軍が、(戯曲の舞台)長崎の沖合の対馬海戦でロシア艦隊に完勝した。」イギリスによって訓練された、というところがイギリス人受けするでしょう。
続けて曰く「西洋は日本に、蓮華の夢と情熱の国のイメージを押しつけようとしたが、半世紀前に黒船によって無理矢理西洋文化との遭遇を強いられた日本は、そこから学んだことを厳格に実証したのである」と(Richard Tames, Pacific Overtures Unwrapping Japan)。つまり、日本は「文明開化」の混乱の中で成長し、西洋が押しつけてきた「オリエンタリズム」の枠からはみ出し始めた、ということですね。 これはある意味で、日本が西洋近代を咀嚼し、「外発」的な開化を「内発」化し始めた第一歩といえるのではないかと思います。
しかし漱石はこの程度では満足しなかったようです。というのも日露戦争の勝利の6年後、1911年の和歌山での『現代日本の開化』という演説の中でも「上滑りの開化」を批判しているからです。でもこの戯曲ではヒロインが日本人なので、現在ではこちらで上演されるときでも基本的に蝶々夫人役は日本人か中国人が演じることが多いようです。イタリア起源の戯曲のヒロインを日本人が演じる(つまり、それが出来る日本人オペラ歌手が存在する)ことが常識となっているのも、それなりに「東洋と西洋の融合」の証左といえるのかもしれません。【2011/6/30】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー