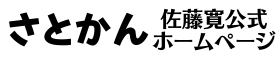【もし今漱石がロンドンにいたら・11】《カズオ・イシグロ》
漱石の小説もいくつか英語に翻訳されていますが、これは漱石が日本の「文豪」になった結果(供給主導)で、必ずしも欧米(英語世界)に漱石のファンが多いわけ(需要主導)ではありません。また、漱石が英語で小説を書いたことはないのではないかと思います。
サセックス大学開発研究所(IDS)の名物教授であるロバート・チェンバース先生(80才近いのにまだまだ元気)の自宅のバーベキューに招かれた時、先生の奥さんが、「私、ハルキ・ムラカミの小説をときどき読むわよ」と言いました。村上春樹がずいぶん翻訳されていることは知っていましたが、イギリス人の読者に会ったのは初めてでした。彼の本は日本語が出るとすぐに英訳されるようで、もちろん彼女はすべて英語で読んでいるわけです。英語にしても売れるだけの需要が十分にあるということですね。
続けて彼女は「でも、ムラカミよりもカズオ・イシグロがもっと好きなのよ」言いました。私はこの作家の名前を知りませんでした。調べてみるとカズオ・イシグロはれっきとしたイギリス現代文学の一流作家でした。1954年長崎生まれ、5歳で家族と渡英して以来ずっとイギリスで英文学を勉強したとのことです。つまり彼は、イギリス人と同じ土台に立って英語で書いているわけです。そこで彼の代表作と言われる『日の名残り(原題:The Remains of the Day)』を読んでみました。
舞台は1956年のイギリス、大英帝国華やかなりし頃からある「執事」という伝統ある職業が焦点です。第二次世界大戦後の英国の凋落、アメリカの台頭などの変化を受けて執事という職業が徐々に意味を失い始めた頃の、ベテランの執事の心に去来する様々な思いを丹念に書き綴った小説です。もちろん全く日本とは縁のない題材ですし、イギリス人だって普通はあまり興味も関心も示さない「執事」というきわめて「特殊イギリス的」な題材を扱っているのです。そしてその日常的な仕事内容まで克明に描写して、イギリス人読者のハートをつかんだのです。これは、どう理解すればいいのでしょう。
この小説の日本語版の解説を丸谷才一が書いていました(関係ありませんが、私がこちらで最初に読んだイギリス小説『ブライトン・ロック』の訳者は丸谷才一でした)。その中で腑に落ちた説明の一つは、「大英帝国の有為転変を、こんなにすつきりととらへることができるのは、(中略)外国系の作家なので、イギリスおよびイギリス人に対し客観的になることができるせい」だというものです。そして「ヘンリ・ジェイムスもコンラッドも、外国系の作家であるせいでイギリスの小説の伝統に深く学び、新しいものをそれに付け加へることができた」と言っています。なぜイシグロが成功したのかの説明としては説得的ですが、この場合、外国人であることは重要ですが、それの出自が日本である必然性はありません。
『日の名残り』を読んだあとたまたま、イシグロのインタビュー記事を見ました。日本のメディアが相手だったせいもあるかもしれませんが「自分の中の日本的なものを、そこはかとなく意識している」というようなことが言われていたように思います。欧米でも通用しているピアニストや、本場のフランスでシェフを張っている日本人などにもしばしば見られるコメントですが、その「日本的なもの」が何であるかを明確に示すことは困難です。「思い込み」である可能性だってあるでしょう。
このブログ『もし今漱石がロンドンにいたら』の原点は、20世紀初頭にロンドンで生活した漱石の「西洋における日本の不在」という慨嘆です。カズオ・イシグロの存在は、日英関係の成熟に伴う西欧文化への日本の侵入の好例です。そんなことが可能になるほど彼我の交流は進化・多様化しているということですね。
こういう状況でもし今漱石がロンドンにいたら、「いっちょう自分でも書いてみるか」と挑戦したに違いありません。題材は、バッキンガム宮殿の騎馬近衛の馬なんていうのは、どうでしょう。【2011/7/8】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー