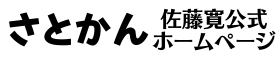【もし今漱石がロンドンにいたら・10】《アポクリフ》
漱石がロンドンにいた頃には西洋舞踏の舞台で日本人が踊る、ということは、まだ想像できなかったでしょう。そもそも当時の鹿鳴館で社交ダンスを踊った日本女性たちは、なれない洋装と慣れない靴で(日本人には靴を履く習慣はなかったのです)、日常生活では決してしないような身体動作をすることに多くの苦痛を覚えたことでしょう。
しかし、そのうち西洋留学経験者で子女にバレエを学ばせる人も出てきて、さらに日本でもバレエを学ぶ機会が徐々に増えていきました。戦後の高度成長期には、ピアノと並んでバレエ教室が叢生し、私の同級生にも何人かそうした教室に通っている人がいたように思います。裾野が広がれば、自ずと国際的にも認められるバレリーナも誕生します。吉田都さんのようにイギリスのロイヤル・バレエ団でプリンシパルをつとめるバレリーナも登場しました。西洋舞踏の本場で日本人がその代表者として踊る、この事態を漱石はどう見たでしょうか。
芸術に国籍はない、という主張はあり得るでしょう。しかし、器楽は楽器に大きく依存し、楽器はその形態・素材ともそれぞれの文化に固有の要素を背負って成立しています。西洋起源の楽器の集積で成り立つオーケストラは当然西洋文化に固有の音楽を奏でることになり、それに乗って踊る舞踏もまた、その身体技法において西洋文化を色濃く反映しています(バレリーナになるためには子供の頃から正座をさせてはいけない、という話を聞いたことがあります)。そして展開するストーリーも(マダム・バタフライなどの例外はあるにせよ)基本的には西洋文化に根ざした物語です。
であれば、西洋舞踏おける日本人の活躍を、西洋身体技法を習得し西洋人以上に上手にそれを用いた舞踏表現さえ出来る、日本人の「器用さ」を象徴するものとして考えるべきなのでしょうか。漱石が書いた「倫敦に住み暮らしたる二年は尤も不愉快の二年なり」の続きは、「余は英国紳士の間にあって狼群に伍する一匹のむく犬の如く、あはれなる生活を営みたり」です。漱石は英国文化を嫌っていたのではありません。むしろそれを評価するからこそ、その中に混ざった自分がまったく一人前の存在感を発揮できないということを嘆いていたのです。だとすれば、日本人プリンシパルがロンドンで踊る様は、まさに漱石の目指していたところなのかもしれません。
しかしそのときに、「日本」はどこに行くのでしょうか。あるいは西洋舞踏の中に「日本」を発見することは狭量に過ぎるのでしょうか。
ロンドンから一番近い海岸沿いの行楽地ブライトンは前衛的な芸術の町として知られ、毎年5月に世界から様々なアーティストを招いた「ブライトン祭り」が行われます。今年のプログラムの中に「アポクリフ」というモダンダンスのパフォーマンスがありました。何の基礎知識もなかったのですがポスターに日本刀を持つ男性の写真があったので何となく気になり、観に行きました。タイトルのアポクリフApocrifuは「聖書外典(apocrypha)」から来ているそうです。
すばらしい公演でした。背景音楽に楽器は一切使われず、7人の男性コーラスのみですが、すばらしく荘厳なハーモニーを奏でていました。踊りは三人の男性ダンサー(あとから知ったのですが一人は日本人でした)がそれぞれにダイナミックに踊ります。モダンダンスを見たのは初めてでしたが、体の柔軟さ、表現力も一流なのだと思いました。明確なストーリーはありませんが、冒頭に旧約聖書(ユダヤ教)、新約聖書(キリスト教)、コーラン(イスラム教)の三冊が登場しました。途中から人形浄瑠璃のような人形も登場します。
このあたりから「日本的」な要素が入り始め、ダンサーの体に「大義」と墨書されていたり、他のダンサーが踊っている時に日本語で「民主主義には大義がない」「本来大義のために死ねる」といった独白が語られます。後半は日本刀のような刀が出てきて三本の刀を三冊の書籍に突き刺します。最後のダンスは操り人形のような状態から抜け出して、激しい踊りになりました。
上演があまりにすばらしかったので家に帰ってからインターネットで調べてみました。公演の中心はベルギーの振り付け家シディ・ラルビ・シェルカウィ、日本人はバレエ出身の首藤康之、もう一人はフランス人でサーカス出身者のディミトリ・ジュルドという人だったようです。独白の台詞は三島由紀夫で、三島がヨーロッパに与えた影響も下地にあるようですし、人形はやはり文楽から着想を得ているようです。実は昨年(2010年)秋に日本で公演されていたようです。
私が興味を覚えた最大の理由は、パフォーマンスの中に「日本」が自然な形で取り込まれていたからなのですが、その理由の一端がウェブにのっていた首藤さんの言葉でわかりました。曰く「日本人の自分が、日本を表現することに恥ずかしさがあった。自分は西洋のバレエにあこがれてきたけれど、日本について語らなすぎると気づいた」のだそうです。これは、西洋舞踏や西洋音楽で一流となった日本人にしばしば見られる語りです。
もちろん、自分の中の日本という出自と縁を切る人もいるでしょうが、西洋芸術を極めたあげくに自分の中の日本を自覚する、という思考経路は「多文化共生」を考える際にとても貴重なヒントを与えてくれます。漱石は、身にそぐわない「外発的な開化」の100年後にこうした境地に達した日本人ダンサーたちの姿を見て、涙を流すのではないかと思うのです。【2011/7/5】
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お知らせ2022.04.04ラマダン休戦
お知らせ2022.04.04ラマダン休戦 イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足
イエメンはどこへ行く2021.12.09迎撃ミサイルの不足 イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション
イエメンはどこへ行く2021.11.03アラブ・コネクション 社会開発2021.10.20アナザーエネジー
社会開発2021.10.20アナザーエネジー